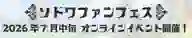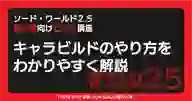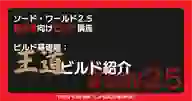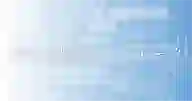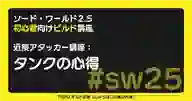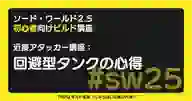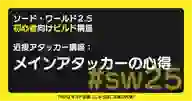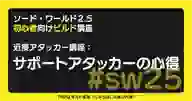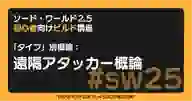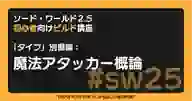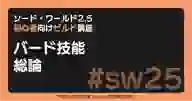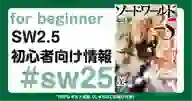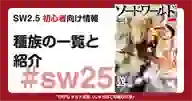SW2.5ビルド「タイプ」別概論 近接アタッカー概論 ソード・ワールド2.5 初心者向けビルド講座
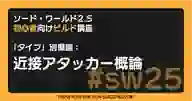
(C)北沢慶/グループSNE
「近接アタッカータイプ」とは?
「近接アタッカータイプ」は剣や槍・拳などの近接武器/格闘武器を使用して、魔物と近距離で戦うタイプです。
メイン技能はファイター・グラップラー・フェンサー・バトルダンサーのいずれか1つを選択することになります。
なお、これらから複数を取ることは(ルール的に禁止されていませんが)主動作が複数になることなどから、かなり渋いです。
「近接アタッカータイプ」の王道ビルド
当サイトでは初めてソード・ワールド2.5を遊ぶ人もキャラクターが作りやすいように、「王道」なビルドを紹介しています!
「近接アタッカータイプ」の王道ビルドとして「全力ファイター」「かばうファイター」「両手利きグラップラー」「必殺フェンサー」「挑発フェンサー」「騎士」を紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。
各技能の特徴
まずは「近接アタッカータイプ」で使用することになる4つの技能について説明します。
ファイター技能
ファイター技能は最もオーソドックスで(一部の「グラップラー専用」の武器・防具を除いて)全ての武器・防具を使うことができます。
鎧を着込んだ 重装戦士をするならファイター技能一択 です。
二刀流のキャラクターをするとしても、ファイター技能は有力な選択肢となります。
レベルが上がると自動取得できる戦闘特技《タフネス》でHPが増えます。
戦闘特技《頑強》《超頑強》を取得すればかなりのHPになります。
グラップラー技能
グラップラー技能はパンチ・キック・〈投げ〉などの技を用いて戦う技能です。
武器はカテゴリ〈格闘〉のものしか使うことができず、防具は「グラップラー装備可能」「グラップラー専用」のものしか使えません。
グラップラー技能を1レベル取得すると戦闘特技《追加攻撃》が自動的に使えるようになる のが大きな特徴です。
これを活かしながら戦うことになります。
戦闘特技《両手利き》を取得すれば、命中力が下がりますが、1回の手番に3回も攻撃ができるようになり、かなり強力です。
〈投げ〉はグラップラーだけができる特殊な攻撃で、相手を「転倒状態」にすることができます。(『ルールブックI』155頁参照)
ただし、〈投げ〉は2H扱いなので、《追加攻撃》が使えないことには注意が必要です。
《投げ強化》《踏みつけ》など〈投げ〉専用の戦闘特技があるため、 〈投げ〉を使う場合は〈投げ〉メイン で考えることになります。
なお、グラップラー技能は戦士系技能の中で唯一「投擲攻撃」を行えません。(『ルールブックI』140頁参照)
あまり使う機会はありませんが、覚えていて損はないでしょう。
フェンサー技能
フェンサー技能はこれらの技能の中で唯一「Bテーブル」の技能です。
必要な経験点が少ないため、他の技能を取得しやすくなること大きなメリットとなります。
装備できる武器・防具の重量が、筋力の値の半分までに制限されます。
しかしクリティカルが少し起きやすくなるというメリットもあります。
戦闘特技《必殺攻撃》を取れば、初期作成でも 4割以上の割合でクリティカルする ようにできます。
バトルダンサー技能
バトルダンサー技能はサプリメント『バトルマスタリー』で追加された技能です。
武器は「グラップラー専用」のものを含め、全てが利用可能ですが、一方で防具にはかなりの制限があります。
戦闘特技を多く取得できることが何よりもの特徴です。
また、レベル7になると自動取得できる戦闘特技《舞い流し》はかなり面白いです。
「近接アタッカータイプ」で考えるべきことは4つ
「近接アタッカータイプ」を考えるとき、大事になるのは以下の4つです。
これら4つを上手に設定することで、活躍できる「近接アタッカータイプ」のキャラクターを作ることができます!
- 敵に武器を当てるための「命中力」
- 武器が当たった敵に与える「ダメージ」
- 敵の攻撃をかわすための「回避力」
- 敵から受けたダメージを減らす「防護点」
「4つも考えないといけないなんて大変……」と思うかもしれませんが、大丈夫です!
以下でそれぞれについて、詳しくみていきましょう。
「命中力」が命
近接アタッカータイプは原則として、 命中しないとダメージを与えられません 。
当たり前のようですが、かなり大事なことです。
攻撃を当てるためには、自分の命中力判定と相手の回避力判定とで「達成値の比べ合い」(『ルールブックI』139頁)を行い、勝つ必要があります。
ソード・ワールド2.5には「受動側優先の原則」(『ルールブックI』106頁)があるので、命中力判定の達成値が、相手の回避力判定の達成値 よりも高くなる 必要があります。
これが意外と難しいです。
命中力の基準について
では命中力がどのくらいだと攻撃が当たるのでしょうか?
『ルールブックI』429頁から先を読み、魔物データを見た上で、どのくらい命中力があると大丈夫かを考えましょう。
初期作成ではボスは多くの場合、魔物レベル3の魔物が選ばれます。
魔物レベル3の魔物のデータを見ると、回避力が4の魔物が多いです。
命中力判定の基準値と魔物の回避力がそれぞれどのくらいだと成功率がどのくらいになるかは、以下の判定シミュレーターを使って簡単に調べることができます。
この際、モードは「達成値の比べ合い」にして、「能動」の「基準値」を命中力判定の基準値に、「受動」の「基準値」を魔物の回避力にしてください。
他の数値はいじらなくて大丈夫です。
結果を言ってしまえば、命中力が5以上ないと、回避力が4の敵には 半分以上の攻撃をかわされてしまいます 。
命中力が6あればそれなりに当たり、7あればほぼ全て当たると思って大丈夫です。
初期作成の場合、 近接アタッカータイプでダメージを与えるなら命中力が「5」以上 と覚えておくと良いです。
命中力を上げる方法
では命中力を上げるにはどうすれば良いのでしょうか?
命中力は「戦士系技能レベル」と「器用度ボーナス」が影響するので、これらを上げるのは大事です。
器用度が高くなる「種族」と「生まれ」を選び、戦士系技能のレベルを2にしておくのが安心です。
命中は高いに越したことはない です。
以下で命中力を上げる方法を紹介します。
戦闘特技
戦闘特技《牽制攻撃》や《斬り返し》を使うことで、攻撃が命中しやすくなります。
少しずるいですが、《両手利き》を使うことで攻撃回数を増やし、結果として命中する回数を増やすことも考えられます。とはいえ《両手利き》は命中力が下がってしまうため、命中率が上がるかは判定シミュレータで計算すると良いでしょう。
武器
武器によっては命中にボーナス修正があります。
特にカテゴリ〈メイス〉の武器はほぼ全て命中がアップするので、命中力が不安なら〈メイス〉を使うのがおすすめです。
〈メイス〉をよく使う人たちから「ソード・ワールドじゃなくてメイス・ワールドじゃん」などと言われるくらい〈メイス〉は便利です。
練技
エンハンサー技能を習得すると、1レベルごとに1つ「練技」を使えるようになります。
練技【キャッツアイ】を取って使用することで命中力を高められます。
エンハンサー技能はBテーブルなので、1レベル取得するのに必要な経験点はわずか500点です。
かなりおすすめの方法です。
魔法
マギテック技能の魔動機術【ターゲットサイト】やドルイド技能の森羅魔法【ウィングフライヤー】はどちらも1レベルから使用可能で、命中力を高めることができます。
ただし、どちらの技能もAテーブルなので、経験点を考えるとおすすめ出来る状況は少ないです。
味方によるバフ・デバフ
味方からバフをもらって命中を高めてもらう、もしくは敵の回避を下げてもらうのもありです。
例えば、初期作成でも使用可能なものとして、以下のようなものがあります。
- 戦闘特技《囮攻撃》
- コンジャラー技能の操霊魔法【ファナティシズム】
- ドルイド技能の森羅魔法【ウィングフライヤー】
- バード技能の呪歌【モラル】
- ウォーリーダー技能の鼓咆【怒涛の攻陣II:旋風】
回避するのか鎧を着込むのか
命中の次に考えるべきなのは、ダメージ……ではなく、回避力もしくは防御点でしょう。
いずれも、敵の近接攻撃に対抗する手段となります。
この2つを両方とも高くするのは大変です。
回避を高くする場合には高い敏捷度が必要であり、防護点を高くする場合には金属鎧を着るために高い筋力が必要です。
また防具には回避力を上げるものと、防護点を上げるものとがあり、どちらを選ぶかによっても性能が変わってきます。
回避力を上げるパターン
回避力を上げる場合、命中力と同様に考えていくのがおすすめです。
つまり、想定される魔物の命中力をみて、どのくらいの回避力が必要か考えてみましょう。
3レベルの魔物の命中力は4〜6ほどです。
回避力が5あれば、半分は回避できそうです。
回避力を上げる方法
回避力を上げる方法としては以下のようなものがあります。
- 回避力が上がる防具
- 戦闘特技《ディフェンススタンス》
- 戦闘特技《回避行動》(レベル3以上なため初期作成では関係なし)
- ドルイド技能の森羅魔法【ウィングフライヤー】
- エンハンサー技能の練技【ガゼルフット】
- ライダー技能の騎芸【攻撃阻害】
- ウォーリーダー技能の鼓咆【流麗なる俊陣I】
他にも敵の命中力を下げるといった方法もあります。
一方で、戦闘特技《全力攻撃》など回避力が下がってしまうものは使いにくくなります。
回避力が高いことによる副次効果
敏捷度が高い場合にはスカウト技能との相性がかなり良いです。
防護点を上げるパターン
防護点を上げる場合は、とにかく金属鎧を着込むのが良いでしょう。
片手武器しか使えなくなりますが、盾を持つことも考えられます。
いずれにせよ、ファイター技能以外は難しいです。
防護点を上げる方法
防護点を上げる方法としては以下のようなものがあります。
- 戦闘特技《防具習熟》
- エンハンサー技能の練技【ビートルスキン】
- アルケミスト技能の賦術【バークメイル】
- ウォーリーダー技能の鼓咆【鉄壁の防陣I】
また、一部の武器には防護点が上がる効果があります。
防護点が高いことによる副次効果
金属鎧を着る場合、スカウト技能や一部の魔法使い系技能との相性が悪くなります。
ただし魔法戦士をする場合、回避力を上げようとすると必要な能力値が多くなり過ぎて難しくなります。個人的には魔法戦士は鎧を着込んで制限を受ける方がおすすめです。
回避力が低くても良いため、戦闘特技《全力攻撃》など回避が下がるものも活用できます。
どちらも低いパターン
パーティーメンバー次第では、回避力も防護点も低くてもなんとかなる場合があります。
例えば味方が戦闘特技《挑発攻撃》や《かばう》を持っている場合です。
戦闘特技《挑発攻撃》や《かばう》を持ったキャラクターについては以下で解説します。
魔法対策について
回避力や防護点を上げることで物理的な攻撃に対処できるようになります。
しかし、魔法の攻撃については効果が薄いです。
また、ガンによる攻撃は回避できますが、防護点は発揮しません。
このような攻撃について、初期作成では対策することはほぼできません。
基本的に精神抵抗力が高い種族・生まれを使うしかありません。特に魔法耐性が高い種族にはグラスランナーやシャドウなどがいます。
ダメージを考える
さて、考えるべきといった4つの要素のうち、「命中力」「回避力」「防護点」について説明を終えました。
最後に「ダメージ」を考えましょう。
ダメージは「威力」「クリティカル値」「技能レベル」と「筋力ボーナス」、そしてダメージを増減する効果によって決まります。
これらのうち、「威力」「クリティカル値」は武器によってが決まります。
ダメージを増やす方法
ダメージを増やす方法としては以下のようなものがあります。
- 戦闘特技《武器習熟》
- 戦闘特技《全力攻撃》
- 戦闘特技《魔力撃》
- エンハンサー技能の練技【マッスルベアー】
- ライダー技能の騎芸【高所攻撃】【チャージ】
- アルケミスト技能の賦術【ヴォーパルウェポン】
連撃
1撃のダメージを増やすのではなく、攻撃回数を増やすことも考えられます。
攻撃回数を増やすことができる方法には以下のようなものがあります。
- 戦闘特技《両手利き》
- 戦闘特技《薙ぎ払い》
- 戦闘特技《追加攻撃》(グラップラー技能)
《両手利き》は命中力が下がってしまう、《薙ぎ払い》は一撃のダメージが下がってしまうという問題があります。
初期作成では活かし難いかもしれません。
クリティカル値
難しいのが「クリティカル値」(C値)です。クリティカル値は 低いほどクリティカルしやすくなり ダメージが増えます。
クリティカルすればダメージが増えますが、威力が低い武器だとクリティカルしても増えるダメージが少ないことが悩みどころです。
しかし威力が高い武器はクリティカル値が高く、クリティカルしにくいです。
どうするとダメージが多くなるかは判定シミュレーターを使って調べてみてください。
クリティカルしやすくする方法
クリティカルしやすくする方法には以下のようなものがあります。
- フェンサー技能の使用
- 戦闘特技《必殺攻撃》
- アルケミスト技能の賦術【クリティカルレイ】
「近接アタッカータイプ」のいろいろなパターン
このページでは「近接アタッカータイプ」の基本について解説しました。
「近接アタッカータイプ」にはいろいろなパターンがあります。
これについては以下で解説していきます。
「近接アタッカータイプ」を使う場合には、ぜひ全部読んでみてください!
「近接アタッカータイプ」の王道ビルド
当サイトでは初めてソード・ワールド2.5を遊ぶ人もキャラクターが作りやすいように、「王道」なビルドを紹介しています!
「近接アタッカータイプ」の王道ビルドとして「全力ファイター」「かばうファイター」「両手利きグラップラー」「必殺フェンサー」「挑発フェンサー」「騎士」を紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。
併せて読んで欲しいページ
当サイトではソード・ワールド2.5初心者の方向けに、キャラクタービルドをいろいろと解説しています!
現在、ビルド講座は 16ページを公開中/随時更新中 です。目次は以下のページにあります。
これらの記事もおすすめです。
キャラクタービルドの他にもお役立ち情報がたくさん!
初心者向けの情報 はこちらにまとめています。
また、ソード・ワールド2.5などのTRPGのキャラクターシートを保管・共有できるWebサービス「ゆとシート」の使い方を以下で公開しています。
「種族や技能ってどんなのがあるの?」って人はぜひ以下のページを見てください。
ぜひどれもご覧ください!